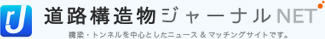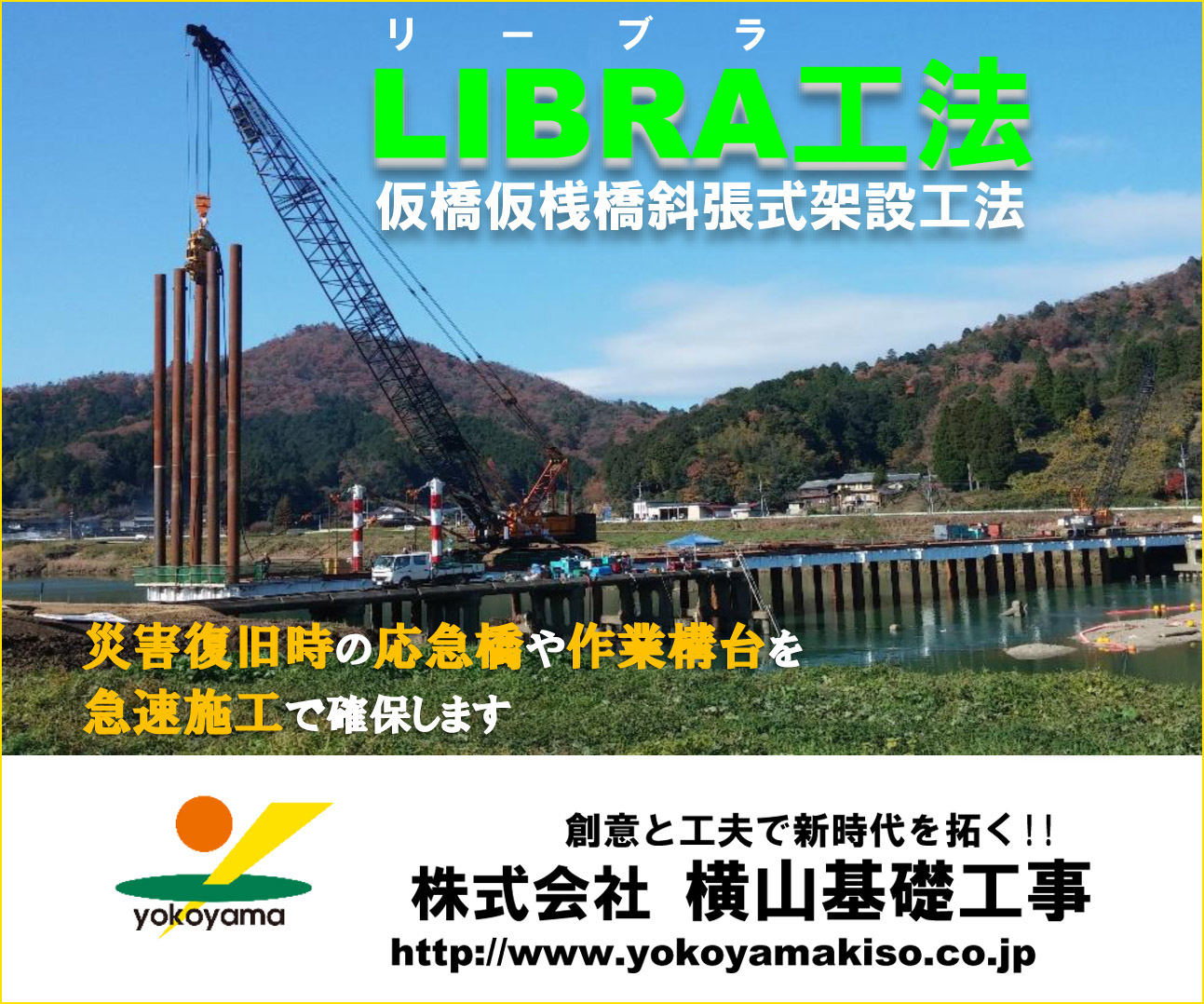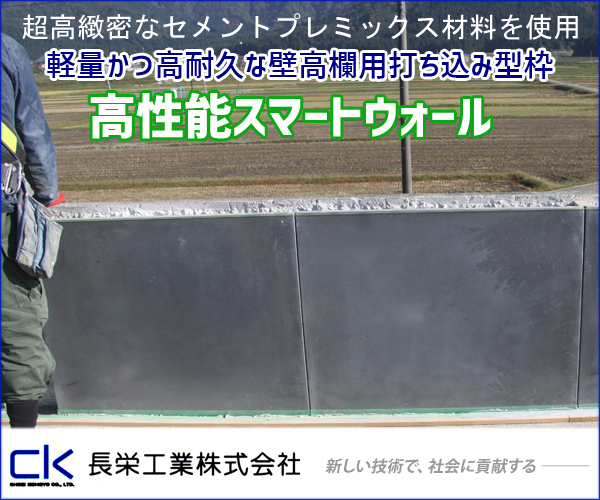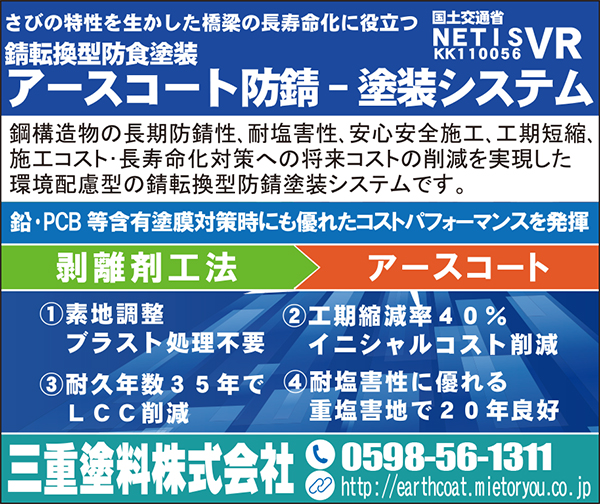3.地方の状況
そこで、地方自治体の状況であるが、まずは、さまざまであるだろう。
まず、
① 県・政令市・中核市……と規模の相違
② それぞれの管理数
③ 財政状況
④ 人員(技術者数)
⑤ 近隣大学
⑥ 近隣企業
――等、さまざまな要因があり、さらには歴史的問題なども影響するだろう。これらを総合的に分析し、自身の戦力を把握することがまず重要である。何が不足しているのか? 冷静に分析する必要がある。
そして、管理している構造物などの実態を見ること、これが重要である。
その時に、目をくらますのが、自己の過大評価とプライドである。
本来、各自治体間には共通の課題も多いはず。それらは、すでに取り組んでいるところを参考し、うまくいっている部分は取り入れて、失敗した部分は反面材料としていけばよいはずである。しかしなかなかできない。そこに県民性や職員のプライド、職員ばかりではなく、首長や議員のプライドなどが入ってくる。そして最大の課題は財政である。
いずれにしても、全国一律というわけにはいかないというのが一つあるが、参考例は世の中にある。いろいろ取り組んでいる先生もいるし、自治体の方々もいる。
最近、ある大学の先生達と話していたら、「橋梁の資料が残っていない。データベース(DB)もできていない自治体が結構ある」ということを言っていた。これも、おそらく各自治体共通の課題である。DBは作る気とお金さえあればできる。この時に大事なのは、ない資料を無理にそろえようとしないことである。最初からプラットホームを作ろうとするのも大変である。1つの自治体が管理するのは橋にすれば、たかだか数千である。資料は敵を知る上でもそろえておく必要がある。
よく言われる例が「役所の体質を変えるのはどうしたらよいか?」「新技術の導入はどうしたらよいか?」「職員の教育は?」という話題であろう。これらは本当に難しい。
私が一つ言えるのは、「それを本当にやる気があるのか?」というところである。やる気があり、やると判断さえすれば、もうほとんどできる。しかしできないのは、やる気もなく古い体質で、やるという言葉だけだからである。
先を見るのは難しい。先が見える人も少ない。しかし、何かヒントがあった場合にどうしていくかというのはそれぞれの判断であるので、何とも言い難い。
4.今回のまとめ
結局は、「人」である。何事、どう感じどう判断し、やるかやらないか?である。
他人の意見を聞けるか聞けないか? ということも同じである。他人の言うことを聞けないのならば、それはそれでそういう判断をしているということなので、別に責める気もないし、「頑張ってください」と言うだけである。
富山で「橋梁トリアージ」と言ったら、みなさん過剰反応した。いまだに言葉だけが取り上げられている。「順番をつける」ことだと思っている人たちがいるが、そうではない。「如何に、どれだけ捨てられるか?」というのが本来の真意である。
現在の2,200橋をどれだけ減らせるか? 減らすのに何年かかるのか? で、市民の将来が変わってくる。八方美人的に良い顔をしていれば、将来どんどん苦しくなる。本来は政治的判断を伴うもので、議会で議論してほしいのだが、公表するとかしないとか? 順番はどうなっているとか? 議論すべきところがずれている。これは、プライドが高く競争心の表れである。トリアージ本来の目的から外れれば何の意味もない。これを理解できるかできないかは、やはり県民性とプライドだと思う。捨てる判断が重要なのだ。富山では結局、理解されなかった。
ということで、今後は「撤去」の判断が重要だと思う。本来、わたしの思いでは数橋撤去していなければならない時期だ。既設橋撤去は、新設するよりも費用が発生する。撤去技術も高度なものが要求される。それを皆どう考えているのか? これを避けるための長寿命化であれば、それはそれで価値があるが、現実を見るとそうはならない。特に市町村。
撤去費用がまた問題になってくると考え、先日、日本橋梁建設協会(鋼橋)とPC建橋に問い合わせてみた。双方とも検討はまだまだだそうである。
しかし、ここで腹が立ったのは、橋建協のお問合せコーナーの回答である。「物価調査会に相談しろ」というのである。驚いた回答である。私は平成8年度に改定された鋼橋の現在の積算基準の大改定に関わった。この時に物価調査会の方々にも大変お世話になったが、このような技術的要素がからむ検討は、失礼ながら体制として無理である。組織によって、可能な事柄と不可能な事柄があるのは当然である。 ということは、今後撤去に関する検討は個別に行わなければならないのだということであり、改めて維持管理の困難さが身に染みた。例えば、NEXCO上のオーバーブリッジの撤去などは早期に行いたいのだが、なかなか予算的に厳しくなることが予想される。こういった問題は、複数の自治体で広域的に検討すべきかと思う。
次回は、けじめとして今後の富山の課題を示したいと思う。
残り1カ月半……!! になりました。今、次に何をやってやるか希望に燃えている自分がいる! どうも私は、変化が好きなのだろう!
(2020年2月16日掲載。次回は3月中旬に掲載予定です)