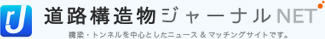『次世代の技術者へ』

⑱鉄道構造物のメンテナンスと相談のしくみ、設計の知識連載
次世代の技術者へ
また緊急事態宣言となってしまいました。私も高齢者に入る世代ですのでコロナにかからないように、特に飲食時は人と距離をとるか、アクリル板で囲むかなど気を付けています。ワクチンや治療薬が行き渡るまではこのようなことの繰り返しがしばらく続きそうですね。注意してもかからないとは言い切れないので、病院の受け入れ態勢さえ問題ないと宣言できれば、皆不安がなくなるのだと思いますが。構造物のトラ…
詳細ページへ
⑰100年を超えても使い続けられている多くの鉄道構造物連載
次世代の技術者へ
あけましておめでとうございます。今年で我国の鉄道開業149年となります。明るい話題として、構造物は十分耐久性を持っているものが多いという話をします。今まで、構造物のトラブルの事例について紹介してきました。しかし多くの構造物はトラブルなくあるいはトラブルがあっても補修して使い続けられています。設計が妥当で、環境が厳しくなければ、しっかりと造られた構造物は十分に100年以上の耐久性を持…
詳細ページへ
⑯鋼橋のトラブルと対策連載
次世代の技術者へ
今まで主にコンクリートのトラブルとその原因などを紹介してきました。国鉄時代の構造物設計事務所(構設)や、JR東日本の構造技術センターでは鋼構造担当のメンバーと一緒に仕事をしてきました。鋼構造物のトラブルの判断は鋼構造の専門技術者に任せていましたが、その主要なトラブルと対処法について紹介します。橋梁は東海道新幹線での騒音問題が生じるまでは、鋼橋が鉄道橋の中心でした。その設計、製作…
詳細ページへ
⑮ 規格や基準の誤解、間違い、不備が原因のトラブル連載
次世代の技術者へ
今回は規格や基準に係る、間違いや誤解での構造物のトラブルの事例ついて紹介します。JISの原案は生産者が中心になってつくられるので、生産者が守られるような規格になり構造物の品質保証にはなっていません。JISの生コンの品質保証は、荷下ろし時点での保証で、構造物のコンクリートを保証はしていません。鉄筋の曲げ戻し試験は、JISにかつては全く規定されていなく、今でもすべてやるような規定にはなって…
詳細ページへ
⑭ たわみで問題となった桁連載
次世代の技術者へ
今回は桁のたわみなど、変形についての話をします。これは特に高速鉄道の問題で、道路ではあまり問題とならないテーマかもしれません。鉄道は運転手が、車両が異常に振動したりすると、すぐに指令という運行のコントロールセンターに報告がされます。その場合、徐行の処置がとられたり、すぐに原因調査が行われます。直接には、車両の異常や、軌道の変位が原因のことが多いのですが、軌道の変位のもとは構造…
詳細ページへ
⑬ RC桁の曲げひび割れと乾燥収縮連載
次世代の技術者へ
鉄筋コンクリートは、ひび割れの発生を前提にしている構造なので、ひび割れが生じるのは当然です。とは言いながら、大きなひび割れが生じるといろいろと問題となります。鉄筋コンクリート桁とPC桁では同じスパンの25m程度で比較するとRC桁のほうが経済的になります。これは国内の積算体系での比較です。そのようなコストの面から、RC桁の最大スパンは25m程度まではつくられてきました。ひび割れが問題となら…
詳細ページへ
⑫構造物の欠陥との付き合い連載
次世代の技術者へ
今回は、構造物の欠陥に係るいくつかの話をします。一つは、欠陥構造物をなくすには、信頼性の高い工法ができたら、それまでの工法をやめていくことの勧めです。さまざまな場面で、変えるべきと思い、提案もしてきましたが、慣れ親しんだ工法をやめるというのはなかなかできないようです。もうひとつは、マスコミなどへの施工欠陥の投書があったことの話です。最後は、落下物が人に当たり、傷害事件となり、…
詳細ページへ
⑪基礎の移動、沈下、地下水の変化による構造物への影響連載
次世代の技術者へ
今回は地盤沈下や支点沈下に伴うコンクリート構造物のひび割れの例と、地下水の変化に伴って対応を迫られた構造物の例とそれと関係する構造の話を紹介します。コンクリート構造物のトラブルとして、ひび割れがあります。前回までに紹介した劣化原因以外にも、温度応力によるものや、基礎や橋脚の移動、沈下が原因で生じるひび割れもあります。温度ひび割れは主にマスコンクリートの施工時の問題で、コンクリ…
詳細ページへ
⑩支承部の損傷連載
次世代の技術者へ
昨年8月に中国の新幹線建設の現場に行ってきました。20年ほど前に中国がまだ新幹線の建設をしていないころ、数年にわたり新幹線の技術協力に関わりました。2004(平成16)年から計画した中国の新幹線の延長は、2018(平成30)年末で29,000㎞の営業となっています。これは日本が55年間で営業した距離の約10倍の距離です。今でも、中国では年間に2,000㎞を開業し、スパン1㎞を超える新幹線の橋梁も1橋は供用し…
詳細ページへ
⑨ 道路 PCグラウト連載
次世代の技術者へ
はじめに今回はPC鋼材の破断についての話をします。戦後に広まったPC構造は、多くの橋に使われています。初期のころは慎重に施工されていましたが、一気に数量が増えたことから、PCグラウトの施工の不十分な橋が多く造られてしまったようです。1.PC構造は戦後に始まるPC構造は、戦時中、鉄道技術研究所にて、吉田徳次郎博士のもとで、仁杉巌博士が若い時に研究していました。戦中には物にならず、戦後、PC枕…
詳細ページへ
⑧塩害(海砂、飛来塩分)連載
次世代の技術者へ
今回は鉄筋腐食にかかわる話の続きですが、塩分がかかわる場合の話をします。塩分の影響は、日本海近くの飛来塩分を受ける構造物と、西日本で問題となった海砂からの塩分とを区別して話します。コンクリート構造物にとっても、鉄筋コンクリートやプレストレストコンクリートなど補強鋼材がある場合は、この塩分は最大の問題となります。かぶりがあっても、水分がなくても鋼材近くに塩分があると鋼材は錆びて…
詳細ページへ
⑦新設構造物のコンクリートの剥落対策連載
次世代の技術者へ
前回、コンクリート片の剥落の原因と、その場合の対策について紹介しました。これも原因は、ほとんど建設時の設計、施工にあります。これから造る構造物が同じようなトラブルの原因とならないための、設計、施工の対応方法について紹介します。1.鉄筋コンクリート鉄筋腐食の原因は、対応できる対策として、コンクリートの中性化への対策と、かぶり不足への対策があります。1.1中性化への対応(1)単位水量…
詳細ページへ
⑥コンクリートの剥落連載
次世代の技術者へ
今回はコンクリート片の剥落についての話をします。ただし塩分が原因の鋼材腐食に関わるものは除いた話題です。塩分が関わるものはそれだけを取り上げて次々回に紹介する予定です。1.鉄筋腐食が原因で鉄筋コンクリートのかぶりの剥落(温和な環境)1.1はじめに高架橋などのコンクリートのかぶりが剥落するということは、かなり前からあり、車を傷つけたりしてはその都度対応していました。近年ではすぐにマス…
詳細ページへ
⑤アルカリ骨材反応(3)連載
次世代の技術者へ
前回、アルカリ骨材反応を生じさせないための対策について話をしたが、今回は、これらのアルカリ骨材反応の生じた構造物の安全性はどうなっているのかについての話をします。1.コンクリートの強度が半分程度になると、鉄筋コンクリート構造物の強度はどうなりますか無筋コンクリートは、割れてしまうと強度は低下するが、ここでは鉄筋コンクリートなど鋼材で補強された構造の話をします。鉄筋コンクリート…
詳細ページへ
④アルカリ骨材反応(2)連載
次世代の技術者へ
前回、アルカリ骨材反応での損傷の生じた構造物について、JISに従って造ったので、施工者に補修費を負担させるわけにはいかないだろうということで、補修費を発注者が負担することとした話をしました。その時に、今後同じ問題の生じる構造物を造ったら、インハウスエンジニアの責任だと言われたことも話しました。すでに経験したトラブルであるので、同じ問題を再び生じさせたら、JISの通り造ったから施工者…
詳細ページへ
③アルカリ骨材反応連載
次世代の技術者へ
もう少し一般的な話を続けようと思いましたが、読むほうが退屈になるかもしれないということで、それは途中に少しずつ加えることにして、今回からは、私の経験を中心に話を進めます。鉄道構造物は、100年程度の径年の構造物も多く現役で使われており、環境と生まれが良ければ劣化するものではないことがわかります。劣化するものには原因があるということです。その劣化原因ごとに、私の経験と、今はどのよう…
詳細ページへ
②鉄道建設の歴史連載
次世代の技術者へ
鉄道構造物まず鉄道構造物の耐久性とメンテナンスに関して、話をしたいと思います。今、50年を超える構造物が増えて、みな寿命を迎えてしまうというような話をする人もいますが、構造物には比較的、短い期間で劣化するものもあり、また100年を超えても健全なものもあります。この古い構造物の状況をまずは知ってもらいたいと思います。古い構造物を知るために、鉄道の建設の歴史を少し紹介します。1.概要鉄道…
詳細ページへ
①私の概歴連載
次世代の技術者へ
最初に執筆をお願いしたのは、8年ほど前だっただろうか。別の会社にいた時に首都高速道路の大規模更新について特集を組んだ。その時に、誰が責任を持って構造物を診るか、というお話を三木千壽先生や、前川宏一先生に聞いた。二人は例えとして国鉄の構造物設計事務所を持ち出された。とりわけ前川先生には、石橋氏が携わった阪神・淡路大震災の時のエピソードとその決断のバックボーンとしての構設の役割につ…
詳細ページへ